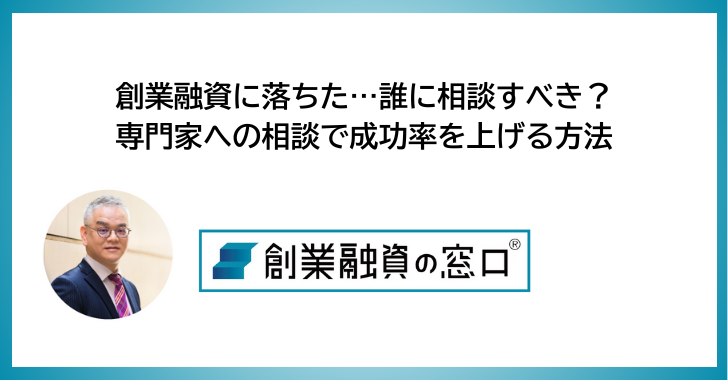ここでしか聞けない”融資を得られる秘訣”を配信中
補助金の最新情報や創業を成功せせる方法
「創業融資に落ちてしまった…」
この一言に、強い落ち込みや不安を感じる人は多いです。
「自分には経営の才能がないのかもしれない」
「もう二度とチャンスは来ないのでは?」
そんなふうに思い込んでしまう人も少なくありません。
しかし、実は多くの人が勘違いしています。
創業融資は「一度落ちたら終わり」ではありません。
むしろ「落ちたあとの行動」で、その後の結果が大きく変わります。
そして、その“結果を決める最大の要素”が何かというと…
「誰に相談するか」です。
この記事では、創業融資に落ちた際に相談すべき相手や、そのメリット・デメリットを解説します。

監修者:太田 耕一郎
コンサレッジ株式会社 代表取締役社長
支援実績537社(2025年10月末時点)に対して、融資実行率93.8%、企業生存率98%を誇る、起業コンサルタント。さまざまな角度から起業を志す人に最適な融資計画やコンサルティングに強みを持つ。
※本コラムでご紹介する内容は専門家および創業融資の窓口®(コンサレッジ株式会社)の監修によるもので、一般的な創業融資を受けるための方法です。
実際には融資を受ける人の状況や業種、ご経歴・ご実績によって、さまざまな方法があります。
「融資やサポートを断られた…」「自己資金がない…」そんな方はぜひ一度ご相談ください!
創業融資再挑戦に強い!
顧問契約で黒字経営を継続!
※本コラムでご紹介する内容は専門家および創業融資の窓口®(コンサレッジ株式会社)の監修によるもので、一般的な創業融資を受けるための方法です。
このコラムでわかること(目次)
一人で悩み続けることの“本当のリスク”
多くの人は、創業融資に落ちた直後、こう考えます。
- もう少し時間を置いてから再挑戦しよう
- 事業計画を自分で直してみよう
- また落ちるのが怖いから準備期間を長く取ろう
一見、慎重で良さそうに見える行動ですが、この「自分だけで何とかしようとする姿勢」こそが、一番の落とし穴です。
理由1:同じ間違いに気づけない
多くの場合、否決された理由は「自分では気づけないポイント」にあります。
計画書の数字よりも、見せ方の問題・聞かれたときの回答の仕方・資金の配分…など、気づきにくい要素が落とされる原因になっていることがほとんどです。
理由2:時間が経つほど状況が悪化する
融資は「タイミング」が命です。
自己資金の残高が減ったり、物件の契約期限が迫ったり、ライバルが増えたり…
時間を置きすぎることで、むしろ条件はどんどん不利になっていきます。
理由3:精神的にネガティブになりやすい
「また落ちたらどうしよう」
「自分には無理なんじゃないか」
そんな不安が大きくなり、行動できなくなってしまう人も実は多くいます。
実際には融資を受ける人の状況や業種、ご経歴・ご実績によって、さまざまな方法があります。
「融資やサポートを断られた…」「自己資金がない…」そんな方はぜひ一度ご相談ください!
創業融資再挑戦に強い!
顧問契約で黒字経営を継続!
※本コラムでご紹介する内容は専門家および創業融資の窓口®(コンサレッジ株式会社)の監修によるもので、一般的な創業融資を受けるための方法です。
なぜ相談することが重要なのか
私がこれまで数多くの創業者を支援してきた中で、
「一度落ちても、その後に成功した人」には明確な共通点がありました。
それは…
「早い段階で“誰かに相談している”」ということ。
落ちた直後に専門家や金融機関、経験者など“第三者”の視点を取り入れることで、
「何が問題なのか」「どう直せば通るのか」を短時間で把握し、
最短ルートで再挑戦できています。
「相談」には2種類ある
ここで大事なのは、ただ相談すれば良いわけではないということ。
当たり前ですが、相談には良い相談と悪い相談の2種類があります。
良い相談ダメな相談
「具体的な改善策を得るための相談」
→ “何を変えれば通るのか”が明確になり、行動に繋がります。
悪い相談
「とりあえず誰かに愚痴を言う」「不安を吐き出すだけ」
→ 気持ちは軽くなりますが、前には進まず、時間だけが過ぎます。
つまり、「誰に相談するか」が最重要となります。
相談先別メリット・デメリット
創業融資に落ちたときに相談できる相手は、大きく4つに分かれます。
- 創業支援の専門家(コンサルタント・中小企業診断士など)
- 金融機関(公庫・信用金庫・銀行)
- 税理士・会計士
- 行政機関(商工会議所・自治体の窓口など)
この4つそれぞれに、「メリット」と「デメリット」があります。
どれが正解というわけではなく、自分の状況に合わせて最適な相談先を選ぶことが大切です。
ここでは相談先のメリット、デメリットを解説していきます。
創業支援の専門家(コンサルタント・中小企業診断士など)
最も成功率が高まりやすいのが、融資支援に特化した専門家です。
彼らは、金融機関が「どこを見ているか」を熟知しています。
メリット
- 審査のポイントを深く理解している
- 事業計画書の「どこが弱いか」をピンポイントで指摘できる
- 面談対策(想定問答、話し方の練習)までサポートしてくれる
- 金融機関とのパイプを持っている場合が多い
- 過去の成功事例を踏まえて、最適な申込先・戦略を選べる
デメリット
- 費用がかかる場合がある(ただし成功率が大幅に上がる)
- 質に差があるため、実績のある人を選ぶ必要がある
上記の点を踏まえ、「最短で確実に通したい」人にとって、創業支援の専門家(コンサルタント・中小企業診断士など)は最も効果的な相談先となるでしょう。
金融機関(公庫・信用金庫・銀行)
創業融資に落ちたときに、「落ちた理由を直接聞けるのでは?」と考え、まず金融機関に相談する人も多くいます。
メリット
- 審査の基準を持っている“本丸”に直接聞ける
- 次に再申請するタイミングや注意点を教えてもらえることもある
- 担当者によっては親身にアドバイスしてくれる
デメリット
- 「なぜ落ちたか」を詳しくは教えてくれないことが多い(たとえば「総合的な判断です」で終わることも)
- 自己流で臨むと、改善点に気づかないまま再挑戦するリスクがある
- 信用金庫や地銀の場合、「紹介者経由」「実績ある専門家経由」の方が通りやすい
金融機関(公庫・信用金庫・銀行)は「情報をもらう場所」ではありますが、「改善まで導いてくれる場所」ではないことに注意が必要です。
税理士・会計士
数字のプロである税理士に相談する人も多いです。
ただし「過去の数字」には強くても、「未来の計画」に強いとは限りません。
メリット
- 決算書や確定申告など、過去の数字の整理には強い
- 税務や会計の信頼感を高めることができる
- 金融機関との付き合いが長い税理士だと、紹介をしてくれることもある
デメリット
- 創業融資(未来の数字)を専門にしているとは限らない
- 事業計画書を“根拠を持って作る”のが苦手な税理士も多い
- 融資の面談対策まではサポートしないことがほとんど
税理士。会計士に相談する場合は「創業融資の経験が豊富な人であるか」を確認すると良いでしょう。
商工会議所・自治体の窓口
「無料で相談できる」という理由で選ばれやすい相談先です。
メリット
- 費用がかからない
- 制度の情報・補助金・助成金の情報を教えてもらえる
- 創業セミナーや面談会などが利用できる
デメリット
- あくまで“一般的なアドバイス”であり、個別・具体的とは限らない
- 事業計画書の細かい指導や面談対策までは踏み込んでくれない
- 担当者によって知識や熱意に差がある
「通すための戦略を練る場所」ではないという点を理解した上で、「制度情報を集める場所」としては有効的に活用ができるかもしれません。
ここまでのまとめ
一人で抱え込む → 同じミスを繰り返し、時間だけが過ぎる
第三者に相談する → 改善点が明確になり、再挑戦の成功率が上がる
しかし、相談先によって得られる結果は大きく変わります。
そして特に「成功率」を重視するなら、最も力を発揮するのが、創業融資に特化した「専門家」への相談です。
では、なぜ専門家が圧倒的に強いのか?
ここからさらに深掘りしていきたいと思います。
専門家に相談することの“本当の価値”
専門家に相談する一番のメリットは、
「自分では見えない落とし穴を、たった1回の会話で見抜いてくれる」ことです。
たとえば…
- 数字のバランスがズレている
- 自己資金の見せ方が悪い
- 面談での回答がズレている
- 金融機関の選び方を間違えている
- 計画の「順序」が不自然(構成の問題)
これらは、自分でいくら勉強をしても気づけないことが多い点です。
しかし、専門家は数多くの実績から、「金融機関が何を重視しているのか」を知っています。
- この業種なら“経験”が最重要
- この支店なら“将来性”を見てくれる
- この担当者なら“人柄”を見る
といったリアルな現場の感覚を持ってるのが専門家です。
そのため、「どの順番で、どこに、どう申請するか」という戦略を立てることができます。
この「戦略」があるかないかで、成功率は大きく変わってくるのです。
「相談しない人」と「相談する人」の差は歴然
相談しない人の特徴
下記の特徴に当てはまる人は、再び落ちることが多い傾向にあります。
- 自分だけで何とかしようとする
- 情報をネットで調べて終わる
- 「たぶん大丈夫だろう」で再申請する
相談する人の特徴
一方、短期間で再挑戦し、成功しているケースが圧倒的に多い人は下記のような共通点があります。
- 自分の弱点を知ろうとする
- 第三者の意見を取り入れる
- 「どうすれば通るか?」を一緒に考える
「うまくいく人」は特別な才能があるわけではありません。
“正しい相談相手”を見つけているだけなのです。
実際の成功事例
ここから、実際に「相談することで成功につながったリアルな事例」を紹介します。
どれも「最初は落ちていた人たち」の話。
しかし、相談をきっかけに状況が劇的に変わりました。
これを読むと
「自分にもまだチャンスはある」と感じられるはずです。
【成功事例①】
独学で申請 → 否決
↓
専門家に相談 → 計画書を根本から改善
↓
再申請で希望額に近い融資を獲得!
東京都でサロン開業を目指していたAさん。
「自分でできるはず」と独学で公庫に申請しましたが、結果は“ゼロ”。
原因は「売上の根拠が曖昧」「計画に実現性が見えない」ことでした。
本人は「数字も内容も間違っていない」と思っていましたが、
専門家が見ると「根拠の提示方法」が弱いことが分かりました。
そこで、専門家と一緒に…
・客単価 × 客数 × 稼働率の算出
・予約の見込み客リストを添付
・内装や機器の見積を揃えて資金使途を明確化
・面談の練習で“数字で語る”訓練
これらを行い、3か月後に再申請。
結果、希望額にほぼ近い融資を獲得しました。
ポイントは「数字そのもの」ではなく「数字の見せ方・伝え方」を変えたこと。
たったそれだけで、結果は大きく変わりました。
【成功事例②】
信用金庫に飛び込みで申請 → 否決
↓
紹介経由で信用金庫に相談 → スムーズに通過!
SNSコンサル業を立ち上げたBさんは、
まず地元の信用金庫に“飛び込み”で申請しました。
しかし「実績がない」という理由で否決。
その後、創業支援の専門家に相談したところ、
「同じ信用金庫でも“紹介経由”で申し込む方が通りやすい」とアドバイスされました。
実は金融機関には
・ 「飛び込み枠」
・ 「紹介者枠」
が存在し、紹介経由の方が“信頼のフィルター”がかかっているため、枠が広くなりやすいのです。
Bさんは紹介を受けて再申請し、
担当者ともスムーズに話が進み、希望額の融資を獲得。
「同じ金融機関」「同じ内容」でも、
“入口の違い”だけで結果が変わるという典型的な成功例です。
【成功事例③】
税理士に依頼したが0円 → 融資専門家が伴走し、2,100万円の調達に成功!
Cさんは、自己資金10万円でカフェ事業を始めたいと考えていました。
「数字なら税理士だろう」と考え、税理士に事業計画書の作成を依頼。
800万円の創業融資を申請しました。
しかし、結果はまさかの「融資0円」。
理由は明確でした。
・未来の売上根拠が弱い
・計画が“希望的観測”に見える
・数字はあるが、“なぜそうなるのか”が説明されていない
税理士は過去の数字には強いですが、
未来の事業計画を「根拠を持って作る」ことが苦手な税理士も多くいます。
Cさんは不安になりながらも、融資に強い専門家へ相談。
そこから伴走支援が始まりました。
専門家と一緒にやったことは…
・12か月の資金繰り表を「悲観・中位・楽観」の3パターンで作成
・市場調査データを追加し、売上根拠を明確化
・広告戦略・集客導線を具体的に落とし込み
・自己資金が少ない分「家計の見直し」「家族のサポート」を証明
・面談の想定問答を“10回以上”繰り返し練習
そして、2か月後に再申請。
結果は…
なんと2,100万円の融資を獲得!
「0円 → 2,100万円」
この劇的な逆転が可能だったのは、
“計画の質”を根本から変えたからです。
Cさんはこう振り返りました。
「自分を否定されたんじゃなくて、計画の伝え方が間違っていただけ。
それに気づかせてくれた専門家に出会えたことが、一番の転機だった」
成功事例から分かること
成功事例からわかることはシンプルです。
“才能”や“運”ではなく
“正しい相談相手を選び”
“正しい改善プロセスを踏めば”
誰でも逆転ができることが分かったかと思います。
自分は“誰に”相談すればいいのか?
ここまで読んで、
「相談が大事なのはわかった」
「でも、自分は誰に相談すればいいの…?」
と思った方も多いのではないでしょうか。
そこで、ここからは
「相談前に準備しておくこと」と「相談相手の選び方」
を実践的に解説していきます。
相談前に「最低限これだけは準備しておくと効果倍増」
相談するだけでも価値はありますが、
“たったこれだけ”準備しておくだけで、相談の質が一気に高まります。
- 現在の状況をまとめたメモ
(落ちた理由・申請金額・業種・悩んでいる点) - 今持っている資料
(事業計画書・資金繰り表・見積書・自己資金の通帳など) - なぜ事業をやりたいのか?という想い
(数字だけでなく、ビジョンや背景も大きな武器になります)
上記は完璧でなくても大丈夫です。「ありのまま」で構いません。
むしろ包み隠さず、“生の状態”の方が専門家は改善しやすくなります。
「誰に相談する?」を判断する方法
ここで、相談先を選ぶ際の“絶対に外せない基準”をお伝えします。
1. 創業融資の実績があるか?
「何件サポートして、どのくらい通しているか?」
“経験値”より“通過実績”が重要です。
2. 数字だけでなく「伝え方」まで指導してくれるか?
事業計画書の“中身”だけでなく、“見せ方”や“話し方”までサポートできる人が理想的です。
3. 面談対策までしているか?
面談は「最後の勝負どころ」。ここを一緒に対策できるかで成功率が大きく変わります。
4. あなたのビジネスを“自分ごととして”考えてくれるか?
テンプレ資料を渡すだけの人は経営者や事業内容をしっかりと見ていない可能性が高いです。
一緒に悩み、一緒に戦略を考える“伴走型”がベストと言えます。
5. 金融機関の“中の事情”を知っているか?
「この支店はこういう傾向」「この担当者はここを見る」など、リアルな現場の感覚がある人は圧倒的に強いです。
創業融資で落ちた後の“再挑戦ステップ10”
ステップ1:否決理由を正確に聞く
「総合的な判断」と言われても粘り強く深掘りする。
ステップ2:自己分析(強み・弱み)を整理する
何が足りなかったのか?数字、経験、資金、伝え方…などしっかりと分析をする。
ステップ3:相談先を「1人」選ぶ
複数ではなく、まずは“信頼できる1人”に絞る。
ステップ4:ありのままを共有する
取り繕ったり、隠したりせず、失敗も含めて全部出す。
ステップ5:再申請の戦略を一緒に立てる
どこに・いつ・いくら・どの順番でを明確にする。
ステップ6:事業計画書を根本から作り直す
「数字の根拠」「裏付け資料」「実現性」を徹底的に強化する。
ステップ7:12ヶ月資金繰り表を準備する
運転資金、季節変動、広告効果まで織り込む。
ステップ8:面談ロープレを繰り返す
“結論→根拠→数字”を自然に話せるレベルまで練習する。
ステップ9:申込先の最適な入り方を考える
紹介経由?専門家経由?支店変更?
(ここで成功率が大きく変わる)
ステップ10:迷う前に申し込む
タイミングを逃さず“勢い”と“準備”のバランスで勝負する。
「一度落ちたからダメなんだ」
そう思う必要は一切ありません。
むしろ――
“弱点が可視化された”と前向きに捉えましょう。
そして、弱点は自分ひとりでは見えにくいもの。
だからこそ、第三者の視点(相談)が必要です。
創業融資は「才能の勝負」ではありません。
“戦略”と“準備”と“伴走者”の勝負です。
まとめ
- 一人で悩むのが一番危険
- 落ちた理由は「自分では気づけない部分」にある
- 相談先次第で結果は大きく変わる
- 特に“専門家”は最短で成功に導くナビゲーター
- “誰を選ぶか”が“いくら借りられるか”を決める
- 正しいステップを踏めば「2~3か月で再挑戦」は十分可能
- 実際に「0円→2,100万」「否決→3か月で700万」「信用金庫NG→公庫300万」などの成功例は山ほどある
「誰に相談すればいいかわからない…」
もしそう思っているなら、
それは“行動が止まっているサイン”です。
あなたが悪いのではなく、
「正しい相談相手をまだ知らないだけ」。
創業融資は、「一人で戦うもの」ではありません。
“伴走してくれるプロ”と一緒に走れば、
成功率もスピードも、驚くほど変わります。
まずは、あなたの状況を話してみてください。
たった30分の会話が、未来を大きく変えることもあります。
「落ちた」ではなく
「まだ途中なだけ」。
今日が、再スタートの一日目です。
「誰に相談すればいいのかわからない」という方こそ、まずは専門家に話を聞いてみてください。第三者の視点が突破口を開きます。
介護事業の創業支援に強い!
黒字経営を経営する融資を目指す
支援実績537社(2025年10月末時点)、融資実行率93.8%、企業生存率98%を誇る、創業融資支援専門会社のコンサレッジ株式会社直下の編集部です。不安や悩みを解決して社長としての第1歩を歩みたい方に創業融資の基礎知識や他では知れない創業融資事情をお届けします。