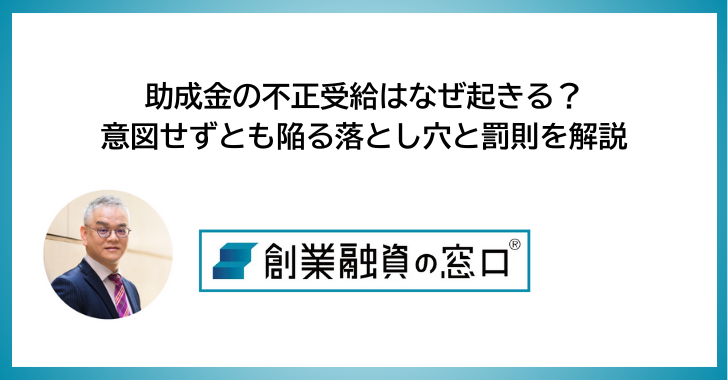ここでしか聞けない”融資を得られる秘訣”を配信中
補助金の最新情報や創業を成功せせる方法
このコラムでわかること(目次)
はじめに
「助成金」と聞くと、“返さなくていいお金”、“国からもらえる制度”というイメージを持つ経営者も多いでしょう。
しかし、その裏側には知られざるリスクがあります。助成金は正しく使えば企業成長の追い風になりますが、一歩間違えば“不正受給”とみなされ、返還命令・刑事罰・社名公表という重大な結果を招くこともあります。しかも最近では、「意図せず不正をしてしまった」経営者の話をよく聞きます。創業融資の窓口に相談に来られる方もいらっしゃいますが、その時点でもう手遅れであることもつらい事実。
そんな事態にならないように、本記事では、助成金の仕組みから不正受給の実態、経営者が注意すべきポイントを専門家の視点で解説します。

監修者:太田 耕一郎
コンサレッジ株式会社 代表取締役社長
支援実績537社(2025年10月末時点)に対して、融資実行率93.8%、企業生存率98%を誇る、起業コンサルタント。さまざまな角度から起業を志す人に最適な融資計画やコンサルティングに強みを持つ。
※本コラムでご紹介する内容は専門家および創業融資の窓口®(コンサレッジ株式会社)の監修によるもので、一般的な創業融資を受けるための方法です。
実際には融資を受ける人の状況や業種、ご経歴・ご実績によって、さまざまな方法があります。
「融資やサポートを断られた…」「自己資金がない…」そんな方はぜひ一度ご相談ください!
創業融資再挑戦に強い!
顧問契約で黒字経営を継続!
※本コラムでご紹介する内容は専門家および創業融資の窓口®(コンサレッジ株式会社)の監修によるもので、一般的な創業融資を受けるための方法です。
助成金とは? その目的と構造
助成金は、厚生労働省などの行政機関が実施する“雇用や成長支援のための制度”です。
キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、働き方改革推進支援助成金などが代表的で、多くの経営者が聞いたことがあるものでしょう。
補助金との違いは「公募・競争がなく、条件を満たせば原則受給できる」点。
つまり“権利的性格”を持つ制度ですが、そのぶん申請内容の正確性と実態の整合性が極めて重視されます。
不正受給とは? ― 意図的・無自覚の2つのタイプ
厚生労働省では、不正受給を次のように定義しています。
不正受給には、大きく2つのパターンがあります。
① 意図的な不正
虚偽の書類を作成したり、従業員の出勤・雇用期間を改ざんしたりする行為。
悪質なケースでは、複数の社労士やコンサルティング会社が関与することもあります。
②無自覚の不正(意図せず違反してしまうケース)
経営者本人が「不正のつもりはなかった」のに、
- 従業員の雇用実態と申請内容に食い違い
- 書類を外部コンサルタント任せにして内容を把握していない
- 助成金採択後の報告・実施管理を怠った
などで結果的に不正認定されるケース。
厚労省の統計によると、**不正受給の3割近くが“無自覚型”**です。
よくある不正受給の事例
以下のようなパターンが、実際に不正認定されています。
ケース1:従業員の雇用日・退職日のズレ
採用日を前倒しして申請、または退職後も在籍扱いにした例。
監査時に従業員本人への聞き取りで発覚する。
ケース2:書類の“代筆”や“まとめ押印”
外部コンサルタントに一任した結果、虚偽記載をされていた。
本人は「知らなかった」が、不正受給と認定。
ケース3:対象者の実態が条件を満たしていない
短時間労働者を「正社員転換」として申請していた。
勤務時間や賃金条件の整合性で虚偽が判明。
ケース4:コンサルティング業者主導での虚偽申請
“受給できる”と勧誘され、書類を丸ごとコンサルティング会社に代行依頼。
採択後に監査で不備が見つかり、全額返還+3年間の受給停止。
不正が発覚した際のペナルティ
不正が確認されると、次のような措置が取られます。
- 助成金の全額返還
- 加算金・延滞金の支払い(最大で1.5倍近くに)
- 厚生労働省ホームページへの社名・代表者名の公表
- 刑事罰(詐欺罪)による告発の可能性
(出典:厚生労働省「不正受給に対する対応方針」)
実際、社労士事務所ですら不正関与で公表される事例も出ています。
このリストは、厚労省公式サイトで誰でも閲覧可能です。
「知らなかった」では済まされない理由
助成金は最終的に“経営者本人”が責任を負う制度です。
「社労士に任せていた」「コンサルタントに言われた通りにした」では免責されません。
たとえば、ある中小企業では次のようなことが起きました。
【事例1】
コンサル会社の指示通りに書類を提出し、100万円の助成金を受給。
数カ月後、従業員の聞き取り調査で日付の不一致が発覚。
→ 経営者本人が不正受給とされ、全額返還+行政処分。
【事例2】
本人が内容を理解せず印鑑を押していたが、
申請データ上で賃金条件が異なり、監査で虚偽申告と判断。
→「知らなかった」では済まず、刑事告発に。
太田さんコメント(専門家視点)
助成金は“もらえるお金”ではなく、“事業の継続と雇用を支える仕組み”と認識しましょう。
制度の趣旨を理解せずに金額だけを追うと、結果的にリスクの方が大きくなります。
不正受給が一度でも認定されると、その後の銀行融資や補助金審査にも影響します。
実際に「助成金の不正受給が理由で融資が断られた」事例もあるため、助成金の受給は慎重に。
経営者が今すぐできる5つの対策
1. 申請内容を“自分の言葉で説明できるか”を確認
人任せにせず、仕組みを自社で理解する。
2. 書類・データを全て自社で保管
代行会社任せにせず、雇用契約書や賃金台帳の控えを残す。
3. 監査に備え、従業員にも内容を共有
面談での聞き取りで食い違いがないよう、社内で説明会を。
4. 顧問社労士・専門家と定期確認
制度変更や運用ルールが年に数回変わるため、最新情報を追う。
5. “おいしい話”を鵜呑みにしない
「誰でも受給できる」「書類だけで通る」という勧誘には注意。
まとめ
助成金は正しく使えば強力な経営支援ツールです。
しかし、知識不足や丸投げ体制のまま申請すれば、
意図せず“違反者”になるリスクがあります。制度の趣旨を理解し、数字と実態を一致させる。
その姿勢こそが、経営者としての信頼を守る最善の防衛策です。
出典・参考リンク
- 厚生労働省「雇用関係助成金 不正受給事案一覧」
- 厚生労働省「不正受給に対する対応方針」
- 日本経済新聞「助成金不正、社労士も摘発」2024年版
支援実績537社(2025年10月末時点)、融資実行率93.8%、企業生存率98%を誇る、創業融資支援専門会社のコンサレッジ株式会社直下の編集部です。不安や悩みを解決して社長としての第1歩を歩みたい方に創業融資の基礎知識や他では知れない創業融資事情をお届けします。